
各種レーザー・硝子体注射等

各種レーザー・硝子体注射等
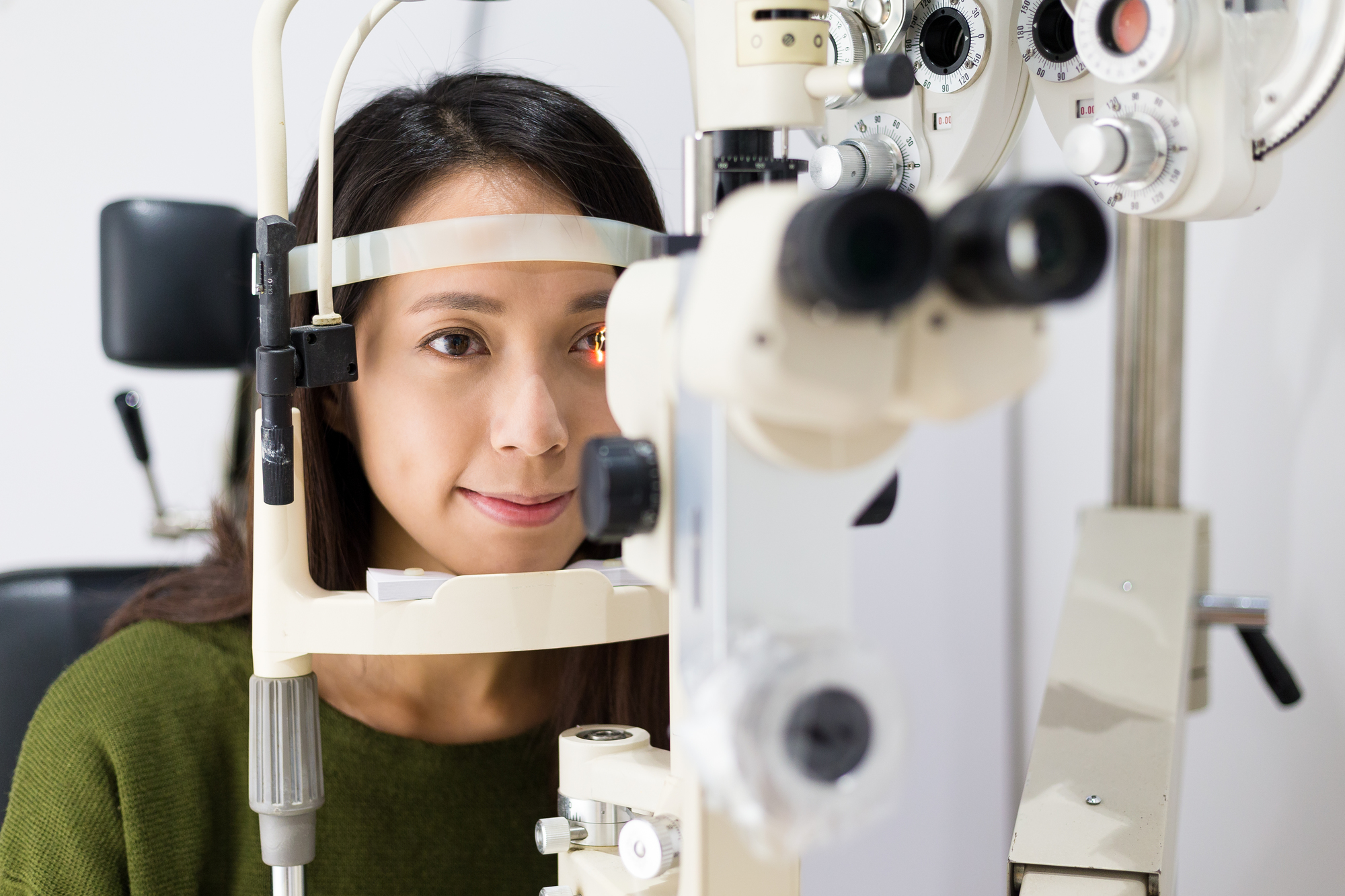
網膜光凝固術とは、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、中心性漿液性脈絡網膜症、網膜剥離・網膜裂孔など眼底の病気に対して行われる治療法です。特定の波長のレーザー光で病的な網膜を凝固させることにより病気の進行を抑えます。この治療法は病気の悪化を防ぐ目的で行われるものなので、元の状態に戻すものではありませんが、これらの眼底の病気には非常に重要な治療法です。
治療は点眼麻酔後、目の表面にレーザー用のコンタクトレンズをのせた状態で行います。時間は病気によって異なりますが、通常1回につき10〜15分程度で終了します。病気によっては、何回かに分けて行うことがあります。
主に後発白内障の治療で行います。
網膜光凝固術が熱を発生させるのに対し、YAGレーザーは衝撃波で濁った薄い膜を破ることで症状を改善させます。
点眼麻酔後、レーザー用のコンタクトレンズを装着し、1回あたり3分程度で終了します。
SLTは緑内障に対する治療法のひとつで、低出力で特殊なレーザーを線維柱帯という部位に照射し、眼球の前方を流れている水(房水)の流れをよくして眼圧を下げます。SLTの効果は、点眼薬1剤分程度といわれており、平均3年程度持続するといわれています。効果には個人差があり、有効率は70%程度といわれています。効果が持続する方もいれば、比較的短期間で効果がなくなってしまう方、残念ながら無効な方もいます。
初回治療で効果がみられた方であれば、効果が弱くなってきたときに再度SLTを行うことで、眼圧下降効果の回復を図ることが望めます。合併症も少なく、痛みもほとんどありません。
点眼麻酔後、レーザー用のコンタクトレンズを装着し、1回あたり15分程度で終了します。
加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、病的近視(脈絡膜新生血管)といった網膜に起こる疾患の原因は、網膜内の血管の異常や網膜下にできてくる新生血管の増殖・成長が原因です。この血管の成長を促すのが、VEGF(血管内皮増殖因子)という物質であることが分かっています。抗VEGF薬療法は、VEGFを抑える薬を眼内(硝子体内)に注射して、新生血管の成長を抑えたり、血管成分の漏れを抑えたりする治療です。
網膜にある静脈が詰まることで、網膜に出血したり、網膜の中心がむくんだり(黄斑浮腫)して見えにくくなる病気です。加齢とともに発症しやすくなりますが、血圧が高い方は発症のリスクが高いといわれています。黄斑浮腫により視力が低下した場合に抗VEGF硝子体注射を行います。
抗VEGF薬は黄斑浮腫に作用し、これを軽減させ、視力の回復を図ります。
初回注射の翌月に診察し、必要に応じて追加の注射を行います。回復がみられた場合は休薬して様子をみます。経過中に再発があれば再度注射をします。
黄斑とは、ものを見るために重要な網膜の中心部です。加齢黄斑変性は、黄斑が加齢とともに異常な変化をきたし、見えにくくなる病気です。加齢黄斑変性には2タイプあり、そのうち新生血管型といわれるタイプは、網膜やその下の脈絡膜に新生血管を生じ、黄斑部に出血やむくみが出ることで視力が低下します。進行が早い場合も多く、放っておくと失明に至ることもあります。
治療には、抗VEGF薬治療や光線力学的療法(PDT)、レーザー治療(網膜光凝固)、硝子体手術などがありますが、現在では抗VEGF薬療法が最も多く行われています。抗VEGF薬を注射することで、新生血管を退縮させ、黄斑部の出血やむくみを減らすことにより視力の回復を図ります。
治療の導入期には、毎日1回の注射を3ヶ月続けます。3ヶ月目以降は診察や検査を経て医師が判断し、必要に応じて注射の間隔を延長したり短縮しながら治療を継続します。再発がない場合は休薬して経過をみることもあります。
糖尿病で血糖が高い状態が続くと、全身の毛細血管が悪くなって問題が起こります。網膜に血管障害が起こると、糖尿病網膜症を発症します。
ひどくなると網膜の中心部である黄斑にむくみを生じたり(黄斑浮腫)、網膜や隅角に新生血管を伴って硝子体出血や血管新生緑内障、網膜剥離などが起こります。その結果、視力が低下したり失明してしまうこともあります。
糖尿病黄斑浮腫の治療として抗VEGF硝子体注射を行います(ほかにレーザー治療やステロイドテノン嚢下注射を行う場合もあります)。
硝子体注射の導入期には毎月1回の注射を4〜5ヶ月続けます。以後は経過をみながら必要に応じて注射を行いますが、効果が出にくい場合もあります。
近視が特に強い眼を強度近視といいますが、強度近視では網膜や脈絡膜が引き伸ばされ、さまざまな眼底の病気を伴います。この状態を病的近視といいます。
病的近視の方の5〜10%に脈絡膜新生血管が発生し、眼底に出血や浮腫(むくみ)を引き起こします。この際視力低下や中心暗転、変視(ものがゆがんで見える)の症状が出現します。
治療には、抗VEGF硝子体内注射が有効です。この薬は新生血管や浮腫に作用し、これを退縮させます。新生血管や浮腫を除去することで黄斑の状態を改善させ、症状の改善を図ります。
はじめに1回の注射を行い、以降は診察や検査を経て医師が判断し、必要に応じて追加の注射を行います。
抗VEGF治療の全身的な副作用には、心筋梗塞、脳梗塞などがあります。
心筋梗塞と脳梗塞は、その既往があるとリスクは高くなり、6ヶ月以内にイベントのあった患者さんには抗VEGF治療は控える場合があります。
抗VEGF治療の眼合併症には眼内炎(感染性・非感染性)、結膜下出血、一過性の眼圧上昇、白内障、網膜剥離、眼内の出血(硝子体出血)などがあります。この中で感染性眼内炎は、頻度は低いものの失明のリスクがあります。
抗VEGF薬にはいくつか種類があり、疾患により適応が決まっています。それぞれに作用の強さや副作用が異なるため、疾患や病態により使い分けています。保険適応ですが、薬剤が高額なため高額療養費制度が適応になる場合があります。
| 3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 | |
| ラニビズマブBSの場合(注射1回につき) | 約26,000円 | 上限18,000円 | 約8,700円 |
| アイリーアの場合(注射1回につき) | 約45,000円 | 上限18,000円 | 約15,000円 |
| ベオビュの場合(注射1回につき) | 約44,000円 | 上限18,000円 | 約15,000円 |
※1割・2割負担の方は、高額療養費制度により1ヶ月でお支払いいただく医療費の上限負担が18,000円と定められています。マイナ保険証(または保険証と併せて限度額適応認定書)を提出していただくと窓口でのお支払いが上限額までとなります。
※上記は片眼のみの費用です。
※診療内容により費用は前後いたします(診察料・検査料などは別途)。
※高額療養費制度の申請については、加入されている健康保険窓口にてご相談ください。